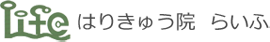不眠症とは?
◦日本は今24時間社会になって、不規則なスケジュールで働く人が増えている。
全体的に見ると、寝るのが下手=「睡眠力の低下」日本人成人5人に1人が、睡眠に問題を抱えている。
◦睡眠不足になると、様々なホルモンの分泌バランスが悪くなる。
ホルモンバランスの乱れが、肥満や糖尿病や高血圧を引き起こす。
◦成長ホルモン
腸・内臓・骨・筋肉などのメンテナンスや細胞の修復などをして、疲労を回復させる。
入眠後、3時間の睡眠の質が重要。
◦睡眠不足の原因
寝る直前まで勉強をする事は脳を興奮したまま、交感神経が緊張、運動して体温が上昇したのと同じ状態。
パソコンなど、明るく強い光を長時間浴びる事も同じ効果。
睡眠障害
◦睡眠に満足できない人300万人
生活習慣や睡眠環境を正しても、日中の強い眠気を感じる。
睡眠時無呼吸症候群
◦睡眠時無呼吸症候群の人300万人
10秒以上の無呼吸状態が、1時間に5回以上あるいは、ひと晩に30回以上起こる。
(日中の眠気が強く集中力が低下、転倒など事故の危険性が高める。)
眠っている間に舌の付け根が下がり、上気道が狭くなり呼吸ができなくなる。
◦症状
大きないびきをかく、あごが小さい、扁桃肥大、鼻の通りが悪いなど。
◦改善方法
⓵今現代人は、咀嚼の機会が少なくなり1回の咀嚼時間が、30分を切った。 咀嚼時間の短さから、徐々に(下や口の)筋力が低下している。
食事の時に咀嚼回数を増やすことと、ガムを噛むなどで咀嚼回数(時間)を増やす。
⓶低めの枕を使う。
(低めの枕⇒気道が確保され、呼吸が楽になる。)
⓷横向きで寝る。
⓸ダイエット。
(腹式呼吸によるダイエット)
◦腹式呼吸と胸式呼吸で、呼吸筋が異なる
胸式呼吸⇒肋間筋(肋骨の間の筋を使う)
腹式呼吸⇒横隔膜(横隔膜・人体で最も大きな筋肉)
◦エネルギー消費量
腹式呼吸>胸式呼吸
むずむず脚症候群
◦むずむず脚症候群の人400万人
身体末端の脚や手の不快感や痛みなどで、眠れない。
(脳の神経細胞が弱まることが原因、鉄分不足や遺伝、加齢などによって症状が出る。)
周期性四肢運動障害
◦周期性四肢運動障害の人はむずむず脚症候群より多い。
脚が勝手に動いてしまう。
(脊髄の興奮がすることが原因、フェリチンの不足、鉄分不足)
◦改善方法
⓵鉄の補給。
⓶ドーパミン受容体作動剤。
枕で改善する方法
仰向きに寝た時に布団の水平面から約15度前傾(さまざまな症状が改善する)
この15度を確かめる方法は?
(手を組み・膝を立て横向きになり・おでこ・鼻・胸が一直線になるように)
マットレスで改善する方法
人間にとって一番、負担の少ない自然な立姿。(S字カーブ)
マットレスまたはタオルなどで(S字カーブ)ができるように調節する。
寝返りができないと血行が悪くなり、心臓への血流量も減り負担がかかる。
◦寝返りの働き
血流や体液などが滞るのを防ぐため、体位を変えて血液循環を促す。
◦硬いマットレス
痛みをとるために、寝返りが増える(力を入れて寝返りをするため、眠りが浅く疲れが取れにくい!)
◦柔らかいマットレス
身体が沈み込むので、寝返りが減る。(血液循環が滞り、寝起きがだるい)
ストレスの開放で改善する
1、不安から抜け出す脳のエクササイズ
自分の心を客観視する力を高めて、思考と現実との違いを見極める。
⇓
「今」を常に考えることで不安の渦から抜け出せる。
軽く目を閉じて
小川と落ち葉を思い浮かべる。
⇓
心の中に浮かび上がる思考を葉っぱに乗せて川に流す。
⇓
考えた事を流すと本当の現実が見えてくる。
2、不安から抜け出すおまじない
・・・・・と思った。
心を客観視する力を鍛えると不安にとらわれない性格に!
◦ストレスで考えすぎて眠れないとき別法
心の中で(あ~)とつぶやく、人間は基本的に頭の中で2つ同時の事を、同時にしゃべることが出来ない。
入眠時に考えすぎると言語中枢が覚醒、起きている時と同じく脳が働いている。
しかし(あ~)と意味のない言葉を心でつぶやく事で、言語中枢を休止させる。
昼間の代謝量を増やし改善する方法
昼間の代謝量を増やし脳の温度を上げれば、よく眠れるようになる。
(運動で代謝量を上げる)
快眠のために、お風呂で体温を1度上げるにはどうすればいいのか?
1、41度のお湯に10分~15分つかれば安全に身体の芯まで温めることができる。
2、入浴は眠る1時間前~2時間前が良い。
3、湯船は温まってから体を洗う。
体内リズムの整え改善する方法
1、早起き。
夜遅くまで起きていても朝早く決まった時間に起きるのが重要。
朝遅く起きると夜なるのが遅くなり生活のリズムが乱れていく。
重要なのは朝起きる時間
起きる時間は6時~8時ぐらいを目安に自分に合った時間を設定
昼寝はすごく大事で、午後2時~午後4時は必ず人間は眠くなる。眠気に襲われる朝起きてから約7時間前後に昼寝をするのは効果的。(昼寝のポイントは長く眠らない事30分以上寝ると夜眠れなくなるため30分以内にとどめることが重要)
2、朝日を浴びて朝食を摂る。
(朝日を浴びると脳の体内時計が毎朝リセットされる)
人間の体内時計は約25時間周期そのため毎朝リセットする事が必要。
朝食を摂ると内臓の体内時計がリセットされる。
(脳と内臓両方の体内時計をリセットする事がリズムを守るポイント)
3、必要な睡眠時間は年齢が上がるにつれ減少。
年齢による睡眠時間
10代8:30 20代7:30 30代6:50 40代6:30
50代6:30 60代6:20 70代5:50 80代5:30
4、眠れない不安がある人。
横になる時間が長いほど古い脳が覚醒。
5、眠れない時は思い切って寝室から出る。
寝つきが悪い時は布団に入らず眠くなるまで待つ
ポイントは布団に入らない。
布団に入る⇒眠れないが続くと(布団=眠れない)余計眠れなくなる。
眠くなって⇒布団に入るこれを繰り返すことで寝つきが良くなる。(行動療法)
6、数日間満足に眠らなくても必要な睡眠は必ず訪れる。しっかり眠気が来てから横になれば眠りの深さも改善。
複合改善法
1、睡眠日誌・2週間
⓵実質睡眠時間
⓶寝床にいる時間
⓷起きたい時間から逆算して入床時間を決める
2、筋弛緩法
筋肉を緊張させたあとに徐々にゆるめる。
(ゆるんでいくときに心地よいと感じとるようにする。)
⓵5秒間力を入れる
⓶糸が切れたように一気に力を抜く
⓷15秒以上、力をゆるめる
⓸緩めている感覚を意識する
行う場所は、眠る30分前に寝室以外の場所で行うとよい。
3、眠気が来るまで寝室には行かない。
4、コーヒーは就寝時間前まで。(個人差はあるがカフェインの覚醒作用は4時間~5時間持続する。)
5、散歩はできるだけ毎日続ける。(できる範囲の家事で活動量アップ。)
6、人との会話で活動量アップ。
7、寝る前はできるだけリラックスタイムに当たると良い。
8、寝る前の運動は避ける。
9、真っ暗にして寝るのは避ける。
10、1度の睡眠⇒約20回の寝返り。(掛け布団の上に毛布を敷く⇒保温効果も良くなる。)
11、睡眠中ひじを冷やさないこと(ひじが冷える⇒肩こり)朝起きたときに疲労感が残る。
七分袖・長袖を着て寝るように!
睡眠に問題があると、リスクが高まる
(高血糖、脂質異常症、高血圧)
◦高血糖のリスク
国民の約6人に1人(2000万人以上)
適切な睡眠時間
7時間~8時間
◦狭心症や心筋梗塞のリスク
適切な睡眠時間
7時間~8時間
7時間~8時間の睡眠をとれば
⇓
夜間に身体が休まる
⇓
血糖値も下がる
深い睡眠がとれていない人の特徴
1、なかなか寝付くことができない。
2、夜中に何度も目が覚めてしまう。
3、早朝に目が覚める。
※1つでも該当すれば可能性あり
深い睡眠をとると
◦脈拍や呼吸がゆっくり。
◦血圧も低下。
◦脳や身体を最も休めることができる。
☆現代は、ストレスや加齢が原因で深い睡眠がとれない人が急増中。
◦睡眠中、特に深い睡眠の時に免疫力が高まる。特に免疫力の中でもB細胞という免疫細胞の活性が高まる。
(B細胞は⇒ウイルスや細菌に力を発揮⇒インフルエンザや風邪等から身を守る)
◦B細胞がつくられるのは
眠っている間+深い睡眠
深い睡眠⇒成長ホルモンが分泌⇒B細胞が作られる
◦B細胞を作る成長ホルモン
就寝後、1時間~2時間の間に深い睡眠をとらないとほとんど分泌されない。
深い睡眠をとる方法
1、寝る2時間前に湯船につかる。
2、寝る1時間前に温かい飲み物を飲む。
就寝前に(体温を上げる)⇒眠る時(体温は下がっていく)
正しい睡眠の必要性
◦睡眠は人間が健康的な生活を送るために細胞の修復や記憶の整理・定着を行う時間。
◦睡眠不足が引き起こす可能性がある重大疾患
寝不足⇒高血圧(脳卒中・心筋梗塞・うつ病・糖尿病)
◦気持ちよく寝付くためのスケジュール
寝る3時間前⇒食事終了
寝る2時間前⇒湯船にしっかり浸かる
◦脳を騙す方法
眠れると考える事で、体がリラックス状態に良質な睡眠につながる。
◦朝に味噌汁を飲めば、夜眠りやすくなる(眠るためのホルモンが出来てくる)
◦短い昼寝のメリット
⓵脳の活動が活発な時に休息を与える事でリフレッシュし効率が上がる。
⓶昼寝前にコーヒーを飲めばスッキリ起きられる。
快眠テクニック
◦寝酒は睡眠には良くない
(お酒は適量を寝る3時間前までに飲めば、リラックス効果が期待できる)
◦なかなか寝付けない方にオススメ
⓵音楽に集中することによって眠れる
⓶就寝前に食事をとると胃腸が活発になり睡眠の質が悪くなる
⓷枕について
男性は高めで硬め
(身体が大きく頭が重いため枕は高めソバガラやパイプなどの硬い素材がオススメ)
女性は低めで柔らかめの枕が良い
(身体が小さく頭が軽いため枕は低め羽毛などの柔らかい素材がオススメ)
⓸布団
男性:硬めで通気性が良い高反発素材
女性:柔らかく熱が逃げにくい低反発素材
⓹湯たんぽ
脳が副交感神経を使って血管を拡張させて熱を外に出す。
(副交感神経=リラックス)
お腹に当てると効果UP
⓺足首クルクル
目覚めた時に、足首を内側に10回・外側に10回・回すと体温が上がり起きやすくなる。
⓻復唱目覚まし
起きる時間を3回唱えてから眠ると、その時間に起きる事ができる。
⓼口すぼめ呼吸
鼻で1秒~2秒吸って、口をすぼめて4秒吐く。
(息をゆっくり吐くことで、リラックスの神経である副交感神経にスイッチが入り眠りやすくなる)
別)睡眠法
◦ベットに入って目を閉じてから10分くらいで眠る脳の構造になっている。
◦1日・15分だけでも早寝をして1ヵ月で7,5時間の睡眠を稼げるので、累積の睡眠量を稼いでいくと改善する。
◦睡眠を十分に取れている、活動すれば分かる。
(起きた時間から4時間後に眠気があるかどうかで判断がつく、起きて4時間後は、脳の働きが一番活発なはずの時間)
◦大体15分寝付けなかったら1時間は眠れない構造になっている。
対処法
◦ベットに入って15分以上眠れないときは一旦ベットから出る。
◦抗重力筋(あごの筋肉を緩める)
(部屋を暗くして、座った状態であごを上に突き出すような感じで、伸ばして5秒ぐらい数えてゆっくり下す・この運動を3回繰り返していると、体の力がちょっと抜けてきて眠くなってきたらベットに入る。)
◦熟睡するためには、寝る1時間前にシャワーで足首を10秒ずつ温める。
足首を温める
⇓
急激に上がった深部体温が下がる。
不眠を考える
◦不眠が続くと
注意力低下
がん
睡眠不足でがん細胞が活性化(免疫細胞の力が低下)
認知症
アミロイドβが神経細胞を傷つける
⇓
睡眠中に脳外へ排出
(糖尿病・高血圧・肥満・心疾患・うつ)のリスクを上昇させてしまう。
◦大切なのは睡眠の質
日本人は、6時間未満の人が40%
◦適正な睡眠時間は6時間半~7時間半と言われています
◦改善法
⓵適度に身体が疲れていた方が入眠しやすくなる
⓶朝日を浴びないでいると、眠りたい時間に眠れなかっりする
(午前10時までに日光を浴びると体内時計がリセットされる)
⇓
睡眠を促すメラトニンが分泌
メラトニンを産生する食材
(バナナ・豆腐・牛乳・納豆・バターなどに含まれる)
睡眠ホルモンメラトニンはトリプトファンからも作られる。
⓷質の良い睡眠に導いてくれる夕食
⇓
鍋(温かい食べ物で上がった体温が就寝前に下がる事で眠気が訪れる)
就寝3時間前までに食事を終える
⓸お風呂も睡眠に重要
人間の体温が下がり始めた時に眠気が訪れる眠る1時間前にぬるめのお風呂にゆっくり浸かるのがおすすめ、水温は38℃~40℃の湯に10分以上かけて浸かる。
⓹昼寝
午後3時以降は夜間の睡眠の妨げになる。
(どうしてもの時は15分だけ仮眠をとるように)
⓺アルコールは睡眠の質を悪くする
⓻寝る前のスマホ
ブルーライトがメラトニン分泌を抑制。
⓼就寝前に気持ちが高ぶると覚醒するホルモンドーパミンが分泌される
⓽睡眠が足りていない時は休みの日にたくさん眠るのは良いことです
(休日に昼過ぎまで眠ると夜2時3時まで眠れない。すると翌日の朝を寝不足で迎える
いつもより1時間遅い時間までに起床する事が大事。)
⓾仰向けに寝るのは要注意(イビキは軽度の睡眠時無呼吸症候群。)
睡眠時無呼吸症候群
⇓
抱き枕で横向き姿勢で寝る
⑪枕が原因で寝返りに影響が出てくる
負担がかからない姿勢は?
自然の立ち姿勢そのままを横にすれば理想的な睡眠時の姿勢
⇓
枕の高さをチェック
究極の起床法
目覚めよく起きるには外からの刺激がないとわからない。
体動(睡眠中に体が動く事)があった時に音を鳴らすシステム。
心地よく目覚める前には体動が頻繁に起こる。
◦良い目覚めとは?
神出鬼没に現れる短時間のごく浅い睡眠のこと。
(明け方になるとだんだん増えてくる)
◦良い目覚めを得るには?
⓵毎日同じ時間に起きていると、その時間にいい目覚めが来やすくなる。
⓶スッキリ目覚めるためには、睡眠時間は最低でも6時間以上を確保する。
◦良い朝をむかえる方法
⓵めざまし時計の音量を小さくする。(20分前にセット)
⓶睡眠時間は最低でも6時間以上を確保。
⓷朝の光を浴びて、朝ご飯を食べる。
睡眠
日本人の4割がある深刻な問題を抱えている⇒睡眠負債
睡眠負債
日々の睡眠不足が積み重なる
日本人の平均睡眠時間⇒6,5時間
6時間未満の人が4割
6時間睡眠を2週間=2晩徹夜
理想的な睡眠時間は7,5時間
週末の寝だめ⇒生活リズムを崩す
週末の夜にいかに深くよく眠るかが睡眠負債を補うポイント!
(夜深く眠るためには昼間に脳を活性化)
◦脳を活性化させる休日の過ごし方は?
脳が活発に働くコミュニケーションをとっている時
(人とのコミュニケーションが大切)
睡眠の解消
(寝付けない・夜中目が覚める・早朝起きてしまう)
60代以上になると6人に1人の方が抱えてる不眠
◦十分な睡眠をとれていないと
(心臓などによる死亡の危険性2,4倍・がん細胞の増殖約2倍。)
◦不眠
⇓
健康長寿に大きな影響を与える脅威
眠れないと訴える人達は40代から増えてくる
(色々な人間関係・仕事・家庭の中で様々なストレスが増えてくる。)
ストレスがかかってくる度に寝られなくなる
中高年以上の方に不眠が多い理由
⇓
ストレスが原因
ストレスと感じた事を寝る前に紙に書く事でストレスを軽減する。
⇓
筆記表現法
(ストレスを感じた出来事やその時の感情などを紙に書き出す)
⇓
筆記表現によって自律神経のバランスを整える事ができて、それによって不眠が改善して睡眠の質が高まってくる。
⇓
ストレスを客観的に見直す
⇓
ストレス軽減
(自律神経安定)
⇓
睡眠状態改善
◦筆記表現法
イギリスなどで不眠症状がある人の治療法として使われている。
◦筆記表現法のやり方
寝る前にストレスを感じた出来事や感情について15分程度書く。
⇓
(ストレスを感じた出来事)
⇓
思い出すだけでなく心の中で整理する。
⇓
じっくり時間をかけて書く。
⇓
書き終わったら、書いた紙を破ったり丸めて捨てたりしても良い。
睡眠の質を上げる方法
◦日本人は平均睡眠時間が少ない。
睡眠不足は様々な症状を引き起こす。
(うつ病・がん・認知症・肥満)
◦最高の睡眠をとるために夕食時にトマトを食べるとよい
最高の睡眠をとるためには体温を下げる事が重要、カリウムや水分の多いトマトは体温を下げる効果がある。
◦最高の睡眠に最も重要なのは眠り始めの90分
90分の質を上げる事が大事。
眠り始めの90分を深い眠りにする
⓵レム睡眠(脳が起きている状態)
⓶ノンレム睡眠(脳が休んでいる状態)
◦最初のノンレム睡眠をいかに深くするかが大切
(眠り始めの90分が深い事で得られるメリット)
⓵自律神経を整える
ストレス・肩こりなどは自律神経の乱れが原因
自律神経を整える
⇓
体調がよくなる
⓶成長ホルモンの分泌
成長ホルモン
(細胞の成長・新陳代謝促進・美肌効果の役割)
成長ホルモン
⇓
最初の深い睡眠で放出
⓷脳のコンディションが良くなる
うつ病・統合失調症の方は最初の深い睡眠が浅いもしくは出ない、これを改善していけば症状が安定する。
良い睡眠⇒症状改善
◦良質な睡眠の方法とは?
⓵トマトを夕食に食べる⇒体温を下げる
⓶就寝90分前に入浴(40℃の湯戦に5分)⇒体温が下がる
⓷就寝前に脳を退屈な状態にする
◦逆にしてはいけないこと、脳に刺激を与える
(眠りのスイッチが入らない)
⓵ミステリーはNG
⓶スマートフォン(就寝1時間ほど前から見ない)
⓷靴下をはいて寝ない(寝ているときは体温が下がる)
⇓
熱が逃げなくしてしまう
⇓
寝る直前に脱ぐのがベスト
◦成長ホルモン
最初に深い睡眠が出ないと分泌されない、正確にいうと何時に寝てもいいが、深い睡眠が出ないと分泌されない。
◦睡眠と覚醒は表裏一体、良い睡眠のためには朝から気を付けないとダメ
良い目覚めに繋がるアラームのセットの仕方は?
2つの時刻でセットする
浅い眠りで起床すること
⇓
良質な目覚め
☆起きなきゃならない20分前と起きる時間にセットする。
◦快眠には毎朝みそ汁を飲む。
(朝、みそ汁を飲むと、夜寝る頃、メラトニンの分泌が高まる)
みそ汁⇒体温上昇、日中の活動意欲を高める
◦最高の睡眠のために朝やってはいけないこと。
激しい運動をすること。
体温上昇⇒下がる⇒昼間眠い⇒眠れない
☆理想は?
散歩(速足ウォーキング)
◦個人差はあるが少なくとも6時間~7時間は寝たほうがいい
いびき
睡眠に問題があり、いびきをかいている人
5人に1人
◦いびきの原因
⓵骨格(顔つき)
アジア人はアゴの小ささや物理的なバランスとして軌道が狭い、そこを無理やり空気が通り抜けるので、いびきになってしまう。
⓶加齢、疲労、お酒
⇓
舌や口の筋肉が緩む
軌道が狭くなり⇒いびきが起きやすくなる
⇓
酸素が取り込まれにくくなってしまう
◦睡眠時無呼吸症候群(日本の患者数 推定900万人・予備軍も含め2200万人以上)
眠っている間に気道が狭くなり呼吸ができなくなる
◦睡眠時無呼吸症候群の症状
⓵日中に眠気が襲う、疲れが取れない
⓶高血圧のリスクも無呼吸によって高まる
⓷不整脈・心不全・狭心症・心筋梗塞とも関係
心臓への負担を放置していると⇒突然死につながる
◦課程で出来る3つのいびき改善法
⓵いびき改善スペシャル朝食
(納豆ご飯・卵焼き・味噌汁・バナナ)
⇓
トリプトファンが豊富な食材
◦メラトニン
(トリプトファン⇒メラトニンに変わる)
睡眠の質を向上させるホルモン
◦いびき・無呼吸⇒眠りが浅いときに出やすい
◦睡眠の質を向上
深い眠りを増やす
⇓
いびき・無呼吸改善
◦トリプトファン
メラトニンに変わるまでのタイムラグがある
メラトニンに変わるまで14時間~15時間以上
◦朝ご飯の内容が睡眠の質の改善に大切
⓶ノンアルコールビール
(ホップ・GABAが睡眠の質を高める効果がある)
⇓
・眠りにつくまでの時間が12分早かった
・睡眠の質が改善
⇓
睡眠の質の改善で深い眠りが増えいびきを減少させる効果が期待
⓷いびき矯正まくら
いびきは仰向けの時に出る傾向があるので出だした時に横に向けてもらうと、空気の通り道が、気道が広がっていびきをしなくなる。
・無呼吸が減る可能性がある。